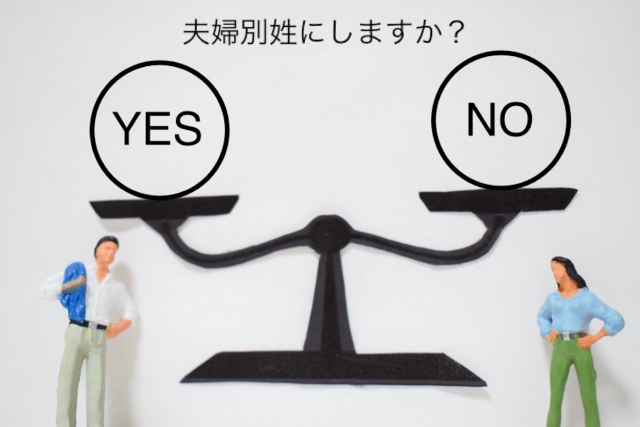選択的夫婦別姓について、私はもともと反対の立場でした。
家族は同じ苗字であるべきで、それが日本の伝統だと思っていたからです。
また、子どもと片親の苗字が異なることで、子どもがつらい思いをするのではないかという懸念もあり、よくない制度だと感じていました。
ところが、夫婦同姓の歴史について調べてみると、実は日本の長い歴史(2685年)の中で、法制度としての夫婦同姓はわずか100年ほどに過ぎないことを知り、目から鱗が落ちました。
明治の後半まで、日本では夫婦別姓が一般的だったのです。
もちろん、当時の庶民には姓がなく、これは公家や武士に限った話ではありますが、夫婦で姓が異なるという在り方は、むしろ日本の伝統に近いのではないかと考えるようになりました。
さらに、明治に夫婦同姓が制度化された背景を調べたところ、それは国家による効率的な戸籍管理・統治のために導入された制度だったこともわかりました。
つまり、これは「伝統」ではなく、近代国家を運営するための行政的な都合だったのです。
そうなると、「夫婦は同姓でなければならない」という考え方に対して、自分の中に疑問が生まれました。
また、「子どもが可哀想になるのではないか」という懸念についても、姓の違いそのものが問題なのではなく、それをどう受け止め、社会がどう支えるかが大事だという意見を聞き、なるほどと納得しました。
そしてもう一つ大切なのは、これは「夫婦別姓を強制する制度」ではなく、「選択できる制度」であるという点です。
選べる以上、それぞれの価値観に基づいて判断すればよく、他人の選択にまで口を出すべきではないと感じるようになりました。
以上のことから、私は選択的夫婦別姓に賛成とはまだ言い切れないものの、少なくとも、かつてのように反対の立場ではなくなったというのが今の率直な気持ちです。
参議院選挙も後半戦に突入し、この選択的夫婦別姓も、投票先を決める争点のひとつとなっているようです。
以前の私のように、「日本の伝統だから」という理由で反対している方もいらっしゃるかもしれませんが、それは歴史的な事実とは異なります。
誰かの強い言葉に引きずられるのではなく、その言葉の裏にある事実や背景を一度立ち止まって考えてみる――
その姿勢こそが、今の時代に求められているのではないでしょうか。